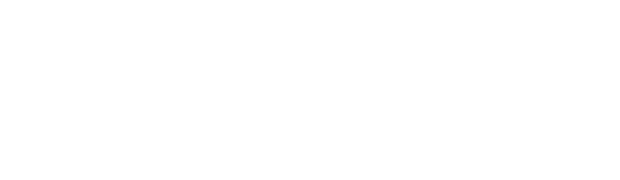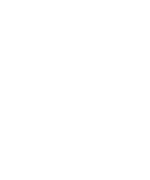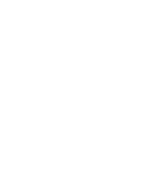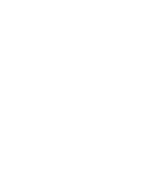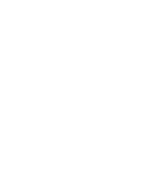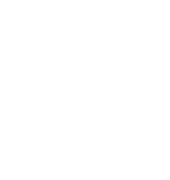最新のご質問に関するご質問
納期に遅れそうな注文が複数ある場合、どれから着手すべきなのか優先度の判断ができません。何か手段がありますか?
DPCには「在庫割れ警告問い合わせ」「在庫割れ警告表」の機能があります。
これらの機能では累積進度の延長で各作業工程の合算在庫数(※)を求めて、在庫で賄えなくなる日付(=在庫割れ日)の特定を行います。
特定された情報は緊急度の高い順(=在庫割れ日の若い順)にリスト表示されますので、このリストを見れば「どの品目のどの工程の作業から着手すべきなのか」作業の優先度が把握できます。
※合算在庫数:当該工程の作業を終えている分の在庫数。上位工程品や上位構成品に組み込まれて姿を変えていても(まだ出荷されず)工場内に留まっていれば合算在庫数として計上される。
タグ:
進捗管理
「どこに何があるのか」「どの工程まで作業が進んでいるのか」を(外注委託分も含めて)を簡単に把握する手段はありますか?
「どこに何があるのか」「どの工程まで作業が進んでいるのか」を把握する為には、単に品目別の在庫を捉えるのではなく、工程間在庫(仕掛在庫)を加工場所別に捉える必要があります。
DPCに実装されている「構成進度問い合わせ」では(初工程から完成工程に至るまでの)すべての工程の在庫数、指示数、実績数が加工先別に表示されますので、必要な情報を一目で把握することができます。
タグ:
在庫管理
進捗管理
これまで仕掛品の資産評価を行う際に「資産評価単価」は「完成品の売価に仕掛品の加工度(%)を乗じた値」としてきたのですが、客観的な評価内容となるよう改善を検討しています。 良い手段は無いでしょうか?
仕掛品の資産評価額は「在庫数×資産評価単価」の式で算定されますが、ここで利用される「資産評価単価」が「完成品の売価に仕掛品の加工度(%)を乗じた値」では、人によって加工度の評価にバラつきがありますのであまり客観的な方法とは言えません。
DPCでは(客観的な方法で)「資産評価単価」を求める手段として「単価積上」の機能を実装しています。
この機能では、構成上最下位の品目から当該仕掛品の当該工程に至るまでの全工程の「取引単価」の値を積み上げることによって「資産評価単価」の算定を行います。
タグ:
在庫管理
遠隔地納入先に納入品の置き場(デポ)があります。この在庫も管理できますか?
DPCのオプション機能に「遠隔地にあるデポ倉庫」を想定した「預け先在庫を管理する為の仕組み」があります。
「社内製品倉庫」から「デポ倉庫」に納入完成品の在庫を移動させ「デポ倉庫」から得意先に納入完成品を出荷することで「デポ倉庫」にある在庫の管理を行います。
この仕組みは「遠隔地にあるデポ倉庫の在庫管理」以外にも「運送業者に代行出荷を委託している場合の運送業者の在庫管理」にも利用できます。
また「デポ倉庫」に対しての「移動指示(何をいつまでにいくつ送ればよいか)」を管理する機能も実装されています。
タグ:
在庫管理
得意先から「トレサビリティのシステム化」について打診があったのですが、容易に対応できそうにありません。 何か良い方法はないでしょうか?
DPCのオプション機能に「後追いトレース」の機能があります。
「トレサビリティ」の基本は「材料から完成品に至るまでのすべての生産工程で使用された部材のロットを記録しそれらの紐付けを行うこと」です。
これを実現する為には、各工程の作業完了時に「作業現場で使用されたすべての部材のロットを逐次記録(入力)すること」が求められますが、現場の作業負荷を考慮すると容易に達成できることではありません。
DPCでは「工場内のすべての工程では必ず『先入れ先出し』を実施している」ということを前提として、各工程で使用された部材のロットを(入力は行っていなくても) "後追い" で自動的に特定する「後追いトレース」の機能を用意しています。
タグ:
ロット管理
現行のシステムでは、一つの品目に対して作業工程毎に複数の品番を設けてマスタ登録を行っています。 これを一つの同じ品番だけで登録(管理)することはできないのでしょうか?
多くの生産管理システムは品番ベースで作られています。作業工程の繋がりは縦一本の部品構成て繋がれているものとみなし、各々の作業工程には仮の構成品として独自の品番を割り当てなければなりません。
これに対してDPCには「品番」とは別に「工程」という概念があります。各々の作業工程は「工程」として取り扱うことが出来ますので、"一つの品番だけ" で管理を行うことが可能です。
勿論DPCにも「品番」の繋がりを「部品構成」として管理する機能を実装していますので、これらを組み合わせることでより実態に近いイメージで品目の管理を行うことができます。
タグ:
マスタ管理
客先からのEDI受注情報では「量産品」と「補給品」が同じ品番で配信されるのですが、自社内ではそれぞれ別の品番で管理を行っています。 受注情報取込時に自社管理品番に変換することはできますか?
DPCには標準機能として 「スズキ様(SPIRITS)」、「ヤマハ様(PYMAC-Ⅲ)」、「ホンダ様(IMPACT-Ⅲ)」 のEDI受注情報取込機能を備えています。
これらの機能には「納入先に応じて品番の変換を行う機能」を実装しておりますで、量産品と補給品の納入先(客先工場内の納品指定場所)が異なっていれば、受注情報取込時にそれぞれ別々の自社管理品番に変換することが可能です。
タグ:
EDI
運送業者に製品の代行出荷を委託しているのですが、運送業者に預けている在庫数が正確に把握できないので過不足が生じてしまい困っています。 解決できる手段はありますか?
DPCのオプション機能に「遠隔地にあるデポ倉庫」を想定した「預け先在庫を管理する為の仕組み」があります。
「社内製品倉庫」から「デポ倉庫」に納入完成品の在庫を移動させ「デポ倉庫」から得意先に納入完成品を出荷することで「デポ倉庫」にある在庫の管理を行います。
この「デポ倉庫」を「運送業者の倉庫」と見立てて運用すれば「運送業者の倉庫にあるすべての製品の在庫数」が把握できるようになります。
タグ:
その他
同一品番で複数の納入先がある場合、出荷準備を行う日程を納入先に応じて変えることは出来ますか?
DPCでは、客先指定の「受注納期」とは別に「出荷予定日(出荷準備を行う日)」という日付を管理してます。
この「出荷予定日」は「受注納期」から「納入先毎に定めた『先行日数』」分の日数を(稼働日ベースで)前倒しすることで自動算定されますので、「先行日数」の値を調整することで納入先に応じた出荷予定日を設定することが出来ます。
タグ:
EDI
受注管理
自動車部品製造会社です。世の中に生産管理システムは多く存在しますが、「協力工場向け生産管理システムDPC」との決定的違いは何でしょうか?
協力工場の生産形態は「繰り返し受注生産型」ですが、確定受注が来てから生産を開始しても納期には間に合わせられないことがあります。(特に自動車関連部品産業ではこの傾向が顕著に見られます。)
この為に「内示で作って確定で出荷する」ことになりますが、内示と確定のギャップにうまく対処できなければ「過剰生産」「生産不足」「納期遅延」が生じてしまいます。
このギャップを捉えながら進捗を管理する為に、DPCでは現場の知恵である「SNS(累積進度管理)」の考え方を取り入れた「構成進度問い合わせ」を実装しています。
タグ:
DPC